先日、ちょうどバレットジャーナルに使っていたノートが終わり、次のノート、ロルバーンダイアリースリム2023に切り替えた。
良い機会だと思ったので、「バレットジャーナル 人生を変えるノート術」(ライダー・キャロル著/ダイヤモンド社)を読み直してみたのだが、新たな気づきがいろいろあった。
この本は数年前にさらっと読み、2020年からバレットジャーナルを始めた。
2年くらいたつが、結構自己流でやっていたこともあり、バレットジャーナルの本質をもう少し取り入れたほうがよいなと思ったし、また新しいノートでのバレットジャーナルに活かしてみようとも思ったので書いてみたい。
本当に大切なことに取り組む
現状のBujo運用
私は基本的にスケジュールはデジタルで管理しているので、今までのバレットジャーナルは、簡単に言うと「タスク管理兼雑記帳」的なものだった。
雑記部分の索引であるインデックス、月ごとのざっくりとした予定とタスクを書いておくマンスリーログ、日々のタスク管理に使うデイリーログ、そして残りのページに雑記からテーマ性のあるカスタムコレクションまでを自由に作る。
キーは原則スケジュールとタスクの2種しか使わない。
また転記がきらいなので、フューチャーログも作らず、todoリストは別冊化した。
「なぜ?」の重要性
別にこれでうまくいっていないわけではなかったが、今回改めて本を読んでみて、バレットジャーナルの本質をあまり取り入れていないのかもしれないということに気づいた。
それは、バレットジャーナルで「頭をすっきりさせて、たくさんのタスクを効率的にこなす」ことが重要なのではなく、「自分の人生にとって本当に大切なことにじっくり取り組む」ことが重要だということ。
これは、私自身が手帳術や時間術が好きで試行錯誤してきたからこそ思うのだが、手帳術や時間術が好きな人が陥る最大の罠は実はコレなのだ。
忙しいからこそ、どんどんタスクをこなして成果をあげたいと頑張るが、最後に我に返ると、結局自分がやってきたのは、自分にとって大切なことではなく、他人(あるいは会社)にとって大切なことだった…となりかねない。
なぜなら、仕事とは基本的には頼まれごとだからである。
著者のライダー・キャロル氏の主張は一貫していて、それは「自分にとって本当に大事なことに集中しよう」ということになる。
なので、常に「なぜ?」を大事にする。
「なぜ、自分はこのタスクをするのか?」
会社員だったころの私のタスクに対する「なぜ」の答えは、「しなくちゃいけないから」というものが多かったかもしれない(というか、当時そんなことを考えもしなかった)。
雇われていると自分がそのタスクを「したいかどうか」より、「しなくてはならないかどうか」で決まることが多いので、ある意味仕方ない部分もあるのだが…。
今は、仕事の部分も会社がお膳立てしてくれることはないので、すべて自分で組み立てなければならない。
その際に、「なぜ、自分はこのタスクをするのか?」は、本当に重要な問いだと思う。
思考の目録
今回改めて読み直していて、そもそもバレットジャーナルのキモはこれだろうと思ったのは「思考の目録」。
- 今実際に取り組んでいること
- 取り組むべきこと
- 取り組みたいこと
まず、この3つを書き出し、そして「なぜ、それをするのか?」を考える。
- 書き出したタスクに対して、それが重要なら目録に残す
- 重要でないもののうち、必要不可欠なものも目録に残す
これで、責務(する必要があること)と目標(自分がしたいこと)が浮き彫りになる。
バレットジャーナルといえば、ラピッドロギングや各種ログなどの書き方ばかりがクローズアップされがちだが、そもそもここから始めないと本当の意味では片手落ちなのではないかと思う。
本書には著者お気に入りの格言がいくつも出てくるが、ドラッカーの次の言葉は、手帳術&時間術好きには結構イタイ(笑)。
そもそも「しなくていいこと」を効率よく実行しようとするのは無駄そのものだ
ピーター・ドラッカー
いくらラピッドロギングで効率を上げようが、そもそもどうでもいいタスクをこなすことに一生懸命になるのは、時間とエネルギーの無駄になる。
ということは、まずタスクそのものを整理する必要があるわけで、本来、バレットジャーナルはこの「思考の目録」からはじめなくてはならないわけだ。
私はこの思考の目録についての記憶がすっかり抜けていたので、結局何をしていたかというと、ブレインダンプだった。
やっぱり何にエネルギーを集中投下すべきなのかをまず考える必要があり、「ではそれをどう料理するか?」という段階でバレットジャーナルは活用できるのだ。
フューチャーログとマンスリーログ
毎月いちいちマンスリーログのカレンダーを作るのが好きではないので、12か月分のカレンダーをノートの前のほうに作る。
なので、フューチャーログを兼ねることができる。
そういう事情もあり、今回はマンスリーページ(カレンダー型)がついたダイアリーを買ってみた。
ただ、本来マンスリーログは、カレンダーページとタスクページに分かれる。
ダイアリーのマンスリーページは、あくまでカレンダーページの代わりであって、タスクページはやはりあったほうがいいと感じた。
しかもスケジュールはもともとデジタルで管理していて、紙に書くのはざっくりとした予定や曖昧な予定が多い。
結局、ダイアリーのマンスリーページは、フューチャーログの代わりを果たしている。
いわゆる、来月以降の予定やタスクをメモしておく場所。
マンスリーログは、どちらかというとマンスリーのタスクを書く場所として、毎月作ることにした。
そして細かなtodoは、分冊化したtodoノートの当該月のページに書き出す。
デイリーログの意義について
まずデイリーログの意義について、これまた結構大きく誤解していたなと思った。
デイリーログとマンスリーログを比べると、
- デイリーログは単なるタスクリストではなく、経験も記録に残せるもの
- マンスリーログは、思考の目録からタスクを持ってきたり、前月の未完了タスクを持ってきたりする
また、デイリーログとカスタムコレクションの違いは、
- デイリーログ:がらくた入れ
- カスタムコレクション:一定の目的に基づく
要は、デイリーログの使い方としては、
- スケジュールプラン
- タスクプラン
- スケジュールログ
- 経験ログ
- 浮かんだ考え
などを書いておくスペースとなる。
つまり、朝の段階ではしようと思っていること(プラン)を書いておくが、1日たったころには、したことや起こったこと、考えついたことなど何でも書いておく備忘録やライフログの性格も帯びてくる。
頭の中にあることをとりあえず外に出すことで、目の前のことに集中して取り組める。
ある意味GTDのinboxにも近いが、これは、著者がADD(注意欠陥障害)であることも関係しているだろう。
ADDの人たちはフォーカスの対象が次々と変わってしまいがちなので、そこに本格的に注意を向ける代わりにノートに書きつけておくことで、安心して目の前のことに取り組めるのではないだろうか。
私も新たなタスク(「あ、あれもしなきゃ」)が浮かんだら、確かにバレットジャーナルに追記していたが、例えば、アイデアが浮かんだらアイデア帳に1~2言でも書いたり、日記は夜になったら書いたりという感じでわけていた。
ただ、そのやり方は私がほぼ終日自宅にいるからできることだし、また、夜日記を書く段階ではすでに忘れていることもあるのかもしれない。
あるいはもっと重要なことを「タスクじゃないから」と書き逃しているかもしれない。
結局、最終的にどこに転記したり深く展開したりするのかは二の次で、とりあえず浮かんだ瞬間に受け止めるのが本来のデイリーログの使い方なのだろう。
だから「がらくた入れ」という表現が出てくる。
がらくた入れから、必要なものはあとでしかるべきところに移すのだ。
ではなぜ私が、当初この使い方をしなかったかというと、プラン(予定)とログ(記録)が混在するからだった。
私自身は、この2つは絶対に分けたいと考えるタイプなので、バレットジャーナル以前も、書く場所(スペース、アイテム)を分けたり、それができない場合はせめてペンの色を分けたりしてきた。
特に私のデイリーログでは、完了したスケジュールとタスクは赤線を引いて消す。
なので、ログを一緒に書いてしまうと、未完了のプランとログ両方に赤線が引かれないこととなり、何が未完了なのかが非常にわかりにくくなってしまう。
でも、今回はせっかくなので、ルールどおりやってみることにした。
今まで通り、スケジュールは★、タスクは・で書いていくが、そういうプランではなくログに相当するものは、〇で書いてみることにした。
また、それにまつわるメモは、-で追加した。
つまり、〇や-で書いてあるものは、赤線で消込されてなくてもOKだということになる。
この〇や-から、例えば業務ログや日記など必要な専用ノートに移動させていく。
意外と便利だと感じたのは、薬や体調の記録。
例えば頭が痛くなったとしたら、「ズ 12:30 ○○(飲んだ薬)」などの記録を簡単に残せる。
もちろん、体調ノートに書くのが良いのだが、体調ノートを何度も引っ張り出さなくても、とりあえずデイリーログに書いておいて、あとで1日分をまとめて転記しておけばよい。
また、他人と会った記録もスケジュールとしては組み込まれているが、そこでどんなことを話したかなどの印象を2,3書いておくのもいい。
こういうのはそれこそ日記にでも書いておかなければ、意外と忘れる。
だが、日記に書くまでに忘れることだってあるのではないだろうか。
移動と振り返り
バレットジャーナルをはじめて試したときに、イマイチだなと感じたポイントのひとつが、転記の多さだった。
本書では「移動(マイグレーション)」と呼ばれているが、要はページ間の転記だ。
転記ミスによってダブルブッキングが起こるかもしれないし、そもそも転記する時間と労力だって無駄だと思う。
ところが、その一見無駄だと思える作業は、そのタスクを吟味しながらいったん頭のなかを通すことでもあるので、結局のところ著者がいう責務と目標(本当に取り組むべきこと)を見つけるためのふるいになっている。
また、この移動は「振り返り(リフレクション)」によってなされる。
朝に振り返り、夜に振り返り、月末・年末に振り返る。
振り返りとは、what(何をするか)とwhy(なぜするか)を見分けるために行うもので、つまり移動は大切なものをよりわける作業なのだ。
本来、バレットジャーナルでは、この移動と振り返りをかなり重要視しているということがよくわかった。
ただ単に文字を転記しているわけではないのだ。
カスタムコレクションの意義について
カスタムコレクションは、バレットジャーナルを拡張するものとされている。
今回の再読の新たな発見として、「カスタムコレクションには目的があるべき」(ただ情報をため込むだけの場所にしない)ということが挙げられる。
著者曰く、「その情報から建設的な行動を起こせるものにすべきで、人生に何の価値も加えないコレクションに無駄な時間を費やしてはならない」という。
例えば、ハワイ旅行に行きたい場合、憧れのスポットの写真を切り貼りしたり、旅行に関する情報をそこにため込んだりしがちだが、旅行を実現するためのプランを練って実行できるようにして初めて意味があるというわけだ。
私はこのカスタムコレクションをどちらかというと雑記帳的にとらえていた。
例えば外出先のカフェで何かアイデアがわいたら、本来はデイリーログに書いてもいいのかもしれないが、私はそのままトピックとして新しいページを作って書く。
そして、帰宅したら、アイデア帳に転記する。
やはり出先で面白い言葉に触れたり、大切な情報を得たら、それをすぐに書き留めるのだが、それをデイリーログではなく、新たなページを作って書いていたので、ぱっと情報を受け止める器というか、本当にほとんど雑記帳的に使っていた。
ところが、カスタムコレクションはもっと「ひとりブレスト」的なページなのだ。
テーマがあり、それについてあれこれ考える。
必要に応じて、サブコレクションも作り、考えを深める。
当然、そこにはモチベーションを明確にするため「なぜそれをするのか(したいのか)」という問いも必要だ。
著者いわく、「課題を解決する記録法」だという。
こうしてみると、バレットジャーナルというのは、本当に「自分にとって大切なことを見極めて、じっくり取り組んで実行していくこと」に重きを置いているノート術だと思う。
結局バレットジャーナルはそれをサポートするためのツールだといえる。
必要なデザインについて
バレットジャーナルといえば、美しかったり、可愛かったりする手作りノートという印象を持つ人も多いだろう。
だが、「バレットジャーナルに唯一必要な絵を描く能力は、まっすぐに線を引けることだ」と著者は言い切っている。
コレクションをデザインする目標は、以下の3つ。
- その機能を最大限に活用すること
- 読みやすいこと
- 持続可能なこと
常にフォームより機能を優先し、またバレットジャーナルは継続することが大事だと強調されているので、華麗なページが作れなくてバレットジャーナルを断念することほど本末転倒なこともないといえるだろう。
著者の以下の言葉は、さすがに本質をついている。
曲がった線や乱暴な字は、人生でポジティブな変化を懸命に起こそうとし、学び続けている人間の証しだ。
ライダー・キャロル(著者)
完璧ではないかもしれないけど、疑問の余地なく美しい。
大切なのは、そのツールを利用して、何を構築していくかだ。
曲がった線と乱暴な字でできたバレットジャーナルを運用している身としては、大変に勇気が湧く(笑)。
実際、2年ほどバレットジャーナル(もどき?)をやってみた感想として、本当に文字さえ書ければバレットジャーナルは誰でもできると思っている。
バレットジャーナルとは結局システムの話であって、決してカタチの話ではないからだ。
カタチは各人が好きなようにすればいい。
以下の記事は、はじめてバレットジャーナルを試したときの感想。
バレットジャーナルに何を求めるのか
というわけで、久々に「バレットジャーナル 人生を変えるノート術」を読んでみて、面白いと思ったところを早速今のバレットジャーナルにカスタムコレクションとしてメモしてみた。
本来は、読書メモや勉強ノートあたりにとるのだが、せっかくなのでこの新しいバレットジャーナル用ノートを使うのに活かしていこうと(そうすれば頻繁に見返せるため)書き連ねていたら、なんと24ページにもなってしまった(ノートの紙面の小ささと自分の字の大きさを考慮していないとこうなる…)。
すでに、このノートが半年もたないだろなという予感がする(苦笑)。
ちなみにデイリーログはもう少し見やすくしたいと考えていたので、日付スタンプを導入。
インクパッドがいらないタイプで押すだけでいいので、簡単だ。
また、今日のページがぱっと開けるように、ロルバーン専用のブックマークも投入した。
いままでフィルム付箋などをつかっていたので、薄いプラでできたブックマークがこんなに便利だとは想像していなかった。
ロルバーンをデイリー使いしている人は、迷わず導入していいアイテムだと思う。
本書は単なる時間節約術や手帳術といった類のものというよりは、著者の人生哲学的なものも多分に含まれたものとなっている。
私自身が年を重ねて残り時間が長くないと思うからこそ、「本当に大事なことに取り組む」ということにとても共感した。
スキマ時間ばかり活用しても意味がないのだ(苦笑)。
現在、バレットジャーナルには関連図書もいろいろあるが、本当にバレットジャーナルを自分のものとして運用したいのであれば、まずこの原典を一読することをお勧めする。
守破離というが、今回、私自身も「守」が甘かったと痛感した。
関連図書やSNSで見られる華麗なバレットジャーナルは、どちらかというと「破」か「離」だ。
多分、この原典を読めば、バレットジャーナルは誰でも簡単に始められるし、簡単にやってみればいいものだということも理解できるのではないだろうか。
もし何らかの理由で本書を読むのを躊躇しているなら、それこそ「なぜバレットジャーナルをしようと思ったのか(興味を持ったのか)?」を考えてみてもいいかもしれない。
その問いの答えを念頭に置いて読んでみると、かなり収穫のある本だと思う。
にほんブログ村
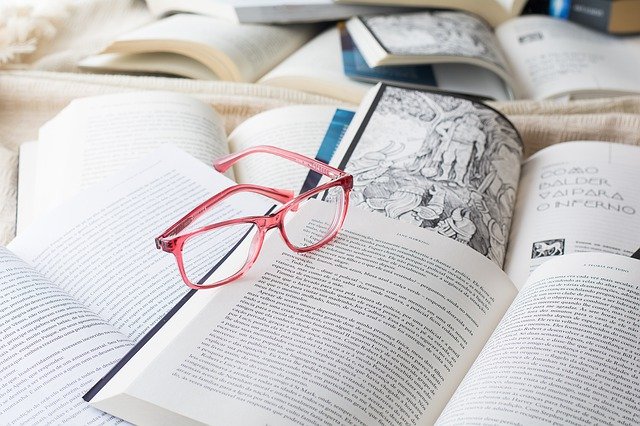






コメント